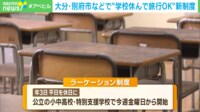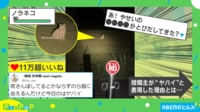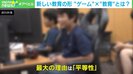「ゲーム」と「教育」。この2つを組み合わせ、学生の新しい教育の形を提案するサミットが3月に行われた。eスポーツを用いた教育とはどのようなものなのか。
最近でこそプロゲーマーやストリーマーという職業が成り立ち、ゲームを競技とするeスポーツが世界中で発達し、広く認知されている。しかし、「ゲームばかりして勉強しなくなるのでは?」というように、教育との相性が良くないと思う人も多いのではないだろうか。
そんなゲームと教育を掛け合わせようと、3月に『第4回eスポーツ国際教育サミット』が開催された。その内容について、主催したNASEF JAPANの坪山義明氏に話を聞いた。
「日本の教育現場で実施しているeスポーツの活用事例や、ゲームやeスポーツが生徒にもたらす影響、学校や教育へのeスポーツの取り入れ方、可能性などについて実例や研究などを踏まえながら紹介している」(以下、坪山氏)
具体的にはどのような発表が行われたのだろうか。
「『マインクラフト』を使った最先端の教育とはどういったものなのか、どんなことができるのかというのをお話しいただいた」
「マインクラフト」とは、オープンワールドのゲームで、世界のすべてがサイコロ型のブロックでできており、ブロックを採取したり建物を作ったりすることができる自由度の高いゲームだ。それがどのようにして教育に結びつくのだろうか?
「自分の見たものをマインクラフト上で作ったり、理想の学校や理想の街づくりといったこともできる」
ゲーム内で建築するにあたって、建物の構造や歴史、必要な材料は何かなど様々なことを自分で考えて行動することが教育・学習につながるという。
ゲームと教育を結び付けようとするNASEF JAPANの取り組みは、“プロのeスポーツ選手育成”が目的ではなく、あくまで“教育とゲームの融合”だという。
「前職は体育教師だったが、別にプロのJリーガーを育てるのが体育の授業ではない。スキルを教えるというよりも、チームワークや団体でいかに活動するかっていうところを教えるのも一つだと思う。ツールとしてeスポーツを使っているだけだ」
ゲームを教育に用いようとした最大の理由は「平等性」にあると坪山氏は話す。
「性差や体力差、年齢も全然関係ないし、海外の方との交流といったところから英語に興味が出てきたりということは、eスポーツを通してできる教育的な効果の一つでもあるかなと思う」
■「なぜeスポーツだと『依存症』という言葉が出てくるのか」
“教育とゲームの融合”について、教育経済学が専門の慶應義塾大学・中室牧子教授に話を聞いた。
━━eスポーツは教育に組み込めるのか?
「スポーツは教育活動の一環だと考えられていて、体育や部活動の教育効果に関する研究はすでに結構ある。就学期にスポーツをやっていると学歴が高くなったり、就職面で有利になると示した研究がある。大学も体育会系が就職に強いと言ったりするわけだが、なぜスポーツをする人が就職で有利になるのかを考えると、おそらく2つほど理由がある」(以下、中室教授)
「1つは、スポーツをやっていると心身の発達が良い。しかし、eスポーツの場合はこういう身体活動を大きく伴うわけではないので、これは当てはまらないかもしれない。一方で、もう1つは、『非認知能力』が身につくからだという話がある。坪山氏も話していたように、リーダーシップ、コミュニケーション能力、社会性、忍耐力などを身につけるのでスポーツは良い影響がある。これはおそらくeスポーツにも当てはまると思う。その意味においては、eスポーツも教育だと言っていいのではないか」
━━eスポーツはゲーム依存症に影響する?
「医学分野の研究では、ゲームが脳の働き、健康に一定程度悪影響があるのではないかという研究が進んでいる。スポーツをやりすぎたときに依存症とは言わないが、eスポーツだと依存症という言葉が出てくるのは少し不思議に感じる。『過ぎたるは及ばざるがごとし』と言うように、スポーツもやりすぎると怪我や健康への悪影響があるかもしれない。副作用はどのような場合にもつきものだと思う。それをどうコントロールするかがとても大事」
━━スポーツに比べ、eスポーツの研究はまだ追いついていない?
「eスポーツは始まったばかりなのもあり研究途上の部分も多い。また、教育の効果はすぐに出ない。5~10年ぐらいのスパンで見ないと効果はわからないのではないか。良い面も副作用もあるので、どういうときにそれが顕在化するかを見極めつつ、良い方法を取っていきたい」
(『ABEMAヒルズ』より)
この記事の画像一覧