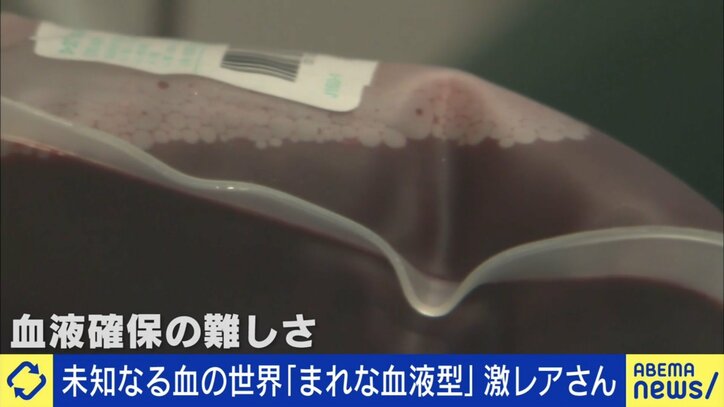■ABO型なら4パターン RH型、実は56パターンも
一般的によく知られるのは「ABO型」で、そこに「RH型」が+、もしくは-というものがよく聞かれるところだ。ところが、現在は47種類もある。神戸学院大学准教授で日本赤十字社に30年以上勤務した坊池嘉浩氏は「みなさんご存知のABO型はA型、B型、O型、AB型の4つだが、たとえばRH型は+、-だけではなく56個もある」と説明した。血液型は遺伝で決まるもので、「抗体」に対して反応する「抗原」があるかないかで判別。定期的に国際輸血学会が承認し、今後も48番目、49番目の血液型が追加される可能性があるという。「昔は生まれたての時に血液型の判定で知ったが、今はほとんどされない。血液型を知っておくことは、自分の個人情報のデータベース。非常に稀な血液型なこともあるので、生活の過ごし方を考えられる」と述べた。
坊池氏によれば47種類の血液型は、健康診断などでは検査せず、また一般的な病院でも調べるところはないという。自身がどのタイプであるかを知るには、やはり献血だ。「まれな血液型の確保を日本赤十字社で行っている。献血に行けば、少なくともABO型と、RH型(+、-)は通知が来る」とし、その他の血液型については、きゃんべるさん☆のような珍しいケースの場合のみ通知が行く。「RH型にnullというのがあるが、これは約200万人に1人」というものもある。
血液型は、輸血の可否に結びつく。全く同じタイプでなければ輸血を受けられない人もいる。そのため通常であれば28日間しか保存できない血液を、日本赤十字社では「まれ血」を冷凍して10年間保存している。きゃんべる☆さんも、2000人に1人のまれ血保持者だけに、定期的に献血に行くようになった。「誰かの助けになるのではないかと。献血をする際に一番大切なのが、ヘモグロビンの数値が足りているかどうか。一番摂るといいと言われているのが肉で、私は豚肉をなるべく摂るように心がけている」と語った。これには坊池氏も「女性は月経もあり、ヘモグロビン濃度が足りなくて献血の基準を満たさない場合がある。そのヘモグロビン濃度をしっかり保つために食事に気をつけられている」と感謝していた。
(『ABEMA Prime』より)