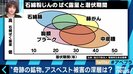知らず知らずのうちにアスベストに侵され、重い病との戦いを余儀なくされた人たちがいる。なぜ、社会問題に発展するまで使用や製造を止めることができなかったのだろうか。
アスベスト(石綿)は繊維状の天然鉱石で、耐熱性・絶縁性・保湿性に優れていることから「奇跡の鉱物」と呼ばれ、ドライヤー、魚を焼くための網、理科の実験器具などにも使われていたほか、戦前から建設資材を中心に自動車や造船など様々な用途に使用され、日本の高度経済成長期を支えた。

しかし、ひとたび体内に吸い込むと、肺がんや中皮腫を発症させる危険性を秘めており、潜伏期間は数十年とも言われている。いつしか、「静かな時限爆弾」と例えられるようになった。

その危険性は70年以上前から把握されていたが、すでに幅広い分野で活用されていたこともあり、国は規制や対策を後回しにしてきた。ついに社会問題として注目を集めたのは、2005年のこと。同年6月、大手機械メーカーのクボタが、旧自社工場の従業員・周辺住民などに、アスベストが原因と見られる疾患での死亡者が78名いたことを発表した。世に言う「クボタショック」だ。「もっときちっと対応できればよかった」。同年7月、細田博之内閣官房長官(当時)はそうコメント、小池百合子環境大臣(当時)も「実態を把握する上で、一体何が有効なのか検討し、専門家グループにおける検討・助言を頂戴していきたい」とし「環境省アスベスト専門家会議」を設置した。

■「40年間かけて絞め殺すようなもの」
「腹が立つのは、『高度経済成長期に厳しく規制したら産業の発展が遅れるから仕方がない』と」と語るのは、損害賠償を求めて国を提訴した原告団の共同代表・岡田陽子さん(満62歳)。

岡田さんが生まれた大阪府泉南市は、戦前から全国屈指のアスベスト工場の集積地だった。1900年頃から操業を開始したアスベスト工場には職を求めて多くの人がやってきた。岡田さんの両親も、1940年代頃から工場に勤務、大量生産時代の1956年に誕生した岡田さんは、工場で長時間働く母親の傍で赤ちゃん時代を過ごしていた。

後に看護師になった岡田さんだったが、30歳を前にアスベスト肺を発症、常に酸素吸入器が手放せない状態の生活を強いられている。両親も同じ病に苦しみ、父親は亡くなった。「子どもが若すぎるので負担をかけたくない。重荷になるのがすごくつらい。母親にはかわいそうだと思うが、『先に逝くからね』とすぐ言ってしまう」と涙ながらに話す岡田さん。母の闘病生活を支える息子は「うまいこと酸素を吸えていない。よく真綿で首を絞めるという表現があるが、ずっと絞めているような状態。10年間、40年間かけて絞め殺すようなもの」と話す。

原告団は、2014年10月9日に最高裁で勝訴を勝ち取ったが、全ての被害者が補償の対象になったわけではない。和解内容は「1958年5月26日から1971年4月28日まで工場でアスベストに曝露する作業に従事した労働者」「アスベスト関連疾患に罹患した」などが条件。工場内で長時間アスベストに曝されていた岡田さんだが、「労働者」には該当しないため補償の対象にはなっていない。「ひとつ区切りはついたなという感じだが、終わったという感じはしない」。
■「死を目前にした人を取材するのが辛くなってくる」10年にわたって寄り添った原一男監督
そんな岡田さんたちを取材、最高裁判決まで記録しつづけてきたのが、ドキュメンタリー映画の鬼才・原一男監督だ。このほど、裁判の過程だけではなく、原告や弁護団の人間模様などを一本にまとめた映画『ニッポン国VS泉南石綿村』が公開される(来月3日から泉南市で先行上映)。昨年には釜山国際映画祭で最優秀ドキュメンタリー賞にあたるメセナ賞、山形国際ドキュメンタリー映画祭で市民賞を受賞した。

8年半にも及んだ撮影について原監督は「こんないい人たちがまだいるんだと思うくらい、原告団の人たちがいい人。どこかでこっちの心が癒される。最高裁判決が出て運動が終わった時に撮影も終わりとなるけど、それがさみしいという感じがするくらいに、この人たちに惚れ込んでいたんだと思う。それが原動力だったのだろう」と話す。
「ごく普通の人たちで、最初から国にケンカを売るという意識はなかった。『何とかしてください、お願いします』と、市民運動の形をとって裁判を始めていった。ところがいくら丁重にお願いしても、国はのらりくらり。裁判で認めてしまうと、補償金というお金の問題になる。だから、できるだけ被害を認めたくない。そこで原告団とぶつかってしまう。クボタは裁判闘争という方法を取らず、大きな騒ぎになる前に見舞金という形でお金を払っちゃえと。運動を進めていた人たちの判断もあったと思う。だけど泉南の人たちはきちんと裁判闘争をやって、国の非を明らかにしようという方法を選んだ」。

上映時間は自身の作品史上最長の3時間35分に及ぶが、描けなかったものもあるという。
「取材をさせてもらった時は元気だった人が、何か月か経ってもう一度話を聞きに行こうとすると、唐突に亡くなってしまっていることもあった。その唐突さがとても残酷に感じた。アスベストの疾患は、ゆっくりしたカーブで同じ速度で悪くなるのではなく、加速度的にひどくなっていく。それがいかに苦しいものかというのを記録しなければならないと思うのだが、死を目前にした人を取材するのが辛くなってくる。苦しい状況を晒すのが忍びないと家族も思う。だから最期まではカメラに撮れなかったし、苦しんでいる実態を世に問いたいと思ったのだけれども、撮れなかった」。
■2030年には解体がピークに、しかし対策は不十分
現在、アスベスト問題で訴訟中の原告は全国で233名おり、その請求総額は約14億円に達する。和解の可能性がある未提訴者は約2300名にも上るという。
ジャーナリストの堀潤氏は「今もなお苦しんでいる方もいるのに、裁判が終わってしまうと、その後の様子は報じられない」と指摘する。「僕は4年間にわたって原発訴訟の取材をしているが、国家賠償訴訟での国側の対応って本当にひどい。裁判所から提出を求められたものについて『探しましたがありませんでした』とか、『ありました。でもよく精査できていません』とか。その間に原告は高齢になったり息切れしたり。周囲の方から無理解な言葉を浴びることもある。裁判を戦うのは本当に負担が大きい」。

原監督も、泉南での判決について「家で奥さんが仕事着を洗濯する時に吸い込んでしまい、発症したというケースもある。そういった場合、因果関係を立証するのは難しくはないのだろうが、『いつからいつまではちゃんと手を打ったんだから』と、国が線引きをしてしまう」と問題点を指摘した。
去年5月、国土交通省は、アパートや事務所などでアスベストが使われた可能性がある建物が6万~8万2千棟ほど残っていると発表した。そのうち、アスベストの飛散を防ぐ措置がとられていない建物は、2万3千~3万棟にも及ぶという。

専門家によるアスベスト分析などを行っているNPO法人、東京労働安全衛生センターの外山尚紀さんは「きちんと解体しようとすると、費用が4、5倍くらいかかる。きちんとやっているところは、ほぼないというくらい稀」と話す。アスベストがどれくらい使用されているか、事前にいくつもの検査が必要になるため、コストが跳ね上がってしまうというのだ。「規制をする法律がいくつもある。厚生労働省は、労働者。環境省は住民。解体現場の周辺の住民。国土交通省は、建物の利用者。3つの役所が別の観点からやっていて、法律も3ある。規制のやり方もそれぞれ違う」。

2030年には耐用年数の限界を迎えた建築物が続々と解体を迫られる事態になる。まさに現在進行系の問題と言えるアスベストの問題に、改めて目を向けるべきだろう。(AbemaTV/『AbemaPrime』より)