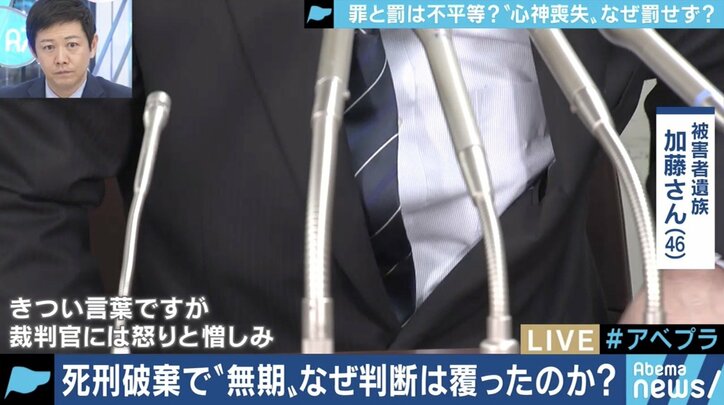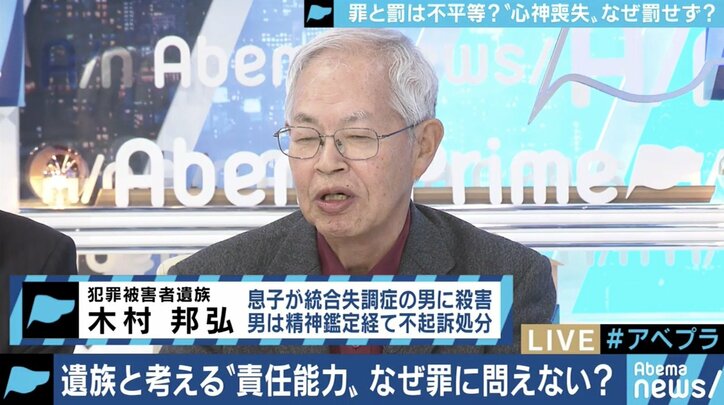埼玉県熊谷市で2015年、男女6人が殺害された事件で、ペルー人のナカダ・ルデナ・バイロン・ジョナタン被告(34歳)の控訴審判決が5日、東京高裁であった。大熊一之裁判長は「何の落ち度もない6名が突然命を失われた結果は誠に重大。責任能力の点を除けば極刑をもって臨むほかない事案だが、被告に対しては心神耗弱による法律上の減軽をすることになる」として一審の死刑判決を破棄、無期懲役を言い渡した。
妻と子どもの命を奪われた被害者遺族の加藤さんは「ここに来るまでは、ひっくり返ることはないだろうと思っていた。(家に)帰って、何て報告して良いか思いつかない」と溜め息混じりに話し、「きつい言葉だが、裁判官には怒りと憎しみ、そして被告人にも、このまま無期懲役であれば、私が解放して殺しに行きたい」と声を震わせた。
裁判で争点となった「責任能力」。刑法39条では、精神障害などで善悪を判断する能力がなく、自らの行動を制御できない状態を「心神喪失」として「罰しない」、また、行為の良し悪しや判断が著しくつきにくい状態を「心神耗弱」として「その刑を減軽する」と定めている。
この規定について、精神鑑定に詳しい吉川和男医師は「ドイツの刑法から輸入された概念で、完全に責任が取れない状態と責任が問える状態との間に“耗弱”という段階を加えた3段階で処遇を決めようというものだ。こういう判断基準は国によって様々で、比較的人権を重んじるヨーロッパの国では一定程度刑を免じようという発想があるが、そうした概念が全くない国もある。ただし、これはあくまでも法的な概念であって、精神障害=責任能力なし、ということではない。実際、複数の方が被害に遭われたような重大なケースでは責任を問われることも多い。また、逆に家庭内や病院内での事件の場合、大半は不起訴になっている。これらは精神科医ではなく、社会的なインパクトを考慮しながら、検察官や裁判官が判断している」と説明する。
「今回の被告については、実際に精神障害があると思うし、ちゃんとした治療を受けていないはずなので、一審、二審の間に病状が進行しているとおそらく出廷している時の病状が段々と重くなっているだろう。そうした様子を見ていると、“犯行当時も重かったのではないか”という判断が出てきてもおかしくはない」。
遺族側代理人の高橋正人弁護士は「責任能力」について、「実務的には、(1)精神障害があるかないか、あったとしてどの程度か。(2)その精神障害が犯行にどの程度の影響を及ぼしたか。(3)善悪を判断する能力があったかどうか、そしてそれに基づいて自分をコントロールできたかどうか。最初の2つは精神科医の判断を尊重しないといけないもので、3つ目は裁判官が判断することだ。法律の勉強を始める時によく言われるのは、“自分のやったことが良いことか悪いことか理解できない人に罪を問うてもしょうがないでしょ”ということ。これには私自身はあまり賛成できない」と話す。
その上で高橋弁護士は「一審は裁判官と9人の裁判員が2週間かけて慎重に判断した。ところが高裁は3人の裁判官が書面だけを見て、訴訟能力はあるが責任能力はないとして無期懲役になった。びっくりした。また、被告は逮捕時に2階から転落して頭を打っており、それが症状にも影響していると思う。裁判が長引いて、症状がどんどん悪くなっていった印象はある。そうなると、裁判で何をやっているのか分からない、訴訟能力がないということで、公判手続きが停止されてしまう」と指摘した。
■「情報を開示してほしい」加害者が不起訴処分となった被害者遺族の訴え
責任能力の欠如が認められた場合、加害者を罪に問えないというだけではない。事件の裁判も行われず、真実を知らされないまま苦しむ被害者家族もいるのだだ。この心神喪失による不起訴件数は、2013年・579人、2014年589人、2015年551人、2016年・507人、2017年・501人に上る。
北海道札幌市に住む木村邦弘さん(74)は、5年前、精神障害者の支援施設で働いていた長男の弘宣さん(当時35)を殺人事件で亡くした。しかし、加害者は統合失調症で、事件前に「お前は死ななきゃならない」との幻聴から、担当していた弘宣さんなら一緒に行ってくれると考え、狙いを定めて包丁で刺殺したという。精神鑑定の結果、心神喪失で責任能力がないと判断され、不起訴処分となった。
母・雅子さんの認知症をきっかけに福祉の道を志した弘宣さん。同僚からも頼られる存在で、仕事にもやりがいを感じはじめていた矢先の出来事。裁判もなく、遺族に公開された情報は“加害者が入院した”という事実だけだった。責任能力がなく、不起訴になった場合、メディアは実名で報じないだけでなく、積極的には報道しないのが現実だ。
「精神障害者の自立支援のための職場で、あってはならないことがなぜ起こったのか」。真実を知りたい、犯罪被害者として全うに扱ってほしいという思いから、問題を訴える活動を続けている。
「事件直後は警察や検察が事情聴取をしてくれたが、責任能力がないとして不起訴になった段階から事件としてはほとんど終わってしまった。そういう意味では加害者もいないし、被害者もいない、つまり“事件”ではないという形だ。だから情報も入ってこないし、置き去りにされたような感じだ。また、施設に対する民事訴訟を検討したこともあるが、息子は事件の加害者が社会復帰をしてもらうために、そこで仕事がしたかった。そういうことについても否定してしまうことになりかねない。施設としても職員を失ったこと、自分たちが社会復帰させようとした仲間が起こしたということで、二重の、非常に大きなショックがあった。また、そもそも民事裁判を起こしても、刑事裁判では不起訴になっているので、資料の提出もできない。その意味でも難しかったし、被害者も加害者も施設側も、今でもきちんとした解決ができないままだ。せめて被害者に対しては他の刑事事件同様、情報を開示して欲しい」。
木村さんは一昨年、「加害者が心神喪失で不起訴になっても一定の情報公開を求める要望書」を法務大臣に提出。昨年には法務省が「被害者や遺族が望む場合、加害者の氏名、現在の状況についても伝えるよう指示」との通達を保護観察所に出している。
「被害者が要望した場合、保護観察所を通じて対象者がどういう処分を受けているか、どこにいるということが分かるようになった。これも大きな前進だとは思っているが、治療が進んでいるのか、事件にどう向き合っているのかといったことは全く出てこない。そうしたことも開示するようになってほしい」。
この点について高橋弁護士は「2000年代にフランスに調査に行ったことがあるが、非常に厳しく、限定的に運用されているので、心神喪失で無罪になることはほとんどないという。また、日本の場合は誤解があり、実況見分調書などを開示すること加害者の更生の妨げになると言われているがそうではない。被害者に開示するのは全く問題ないのに、その法整備がほとんど整っていないことが問題点だ」と指摘する。
■不起訴処分の“その後”「医療観察法」の運用に新たな課題も
では、不起訴処分を受けた加害者はその後どうなるのだろうか。
吉川医師は「日本には医療観察法という法律があり、不起訴あるいは心神喪失が認められた人については治療を行うかどうか、もう一度鑑定する。そこで入院や通院といった処遇が決定され、治療を受けないといけないことになっている。6割は強制的に入院となるが、場合によっては釈放、あるいは刑務所に戻す判断や、責任能力を見直すという判断もある」と話す。
これについて高橋弁護士は「医療観察法ができたのは、加害者が措置入院を短期で解除された後に犯行に及んだ附属池田小事件が起きたことがきっかけだ。それまでは精神科医だけで入退院を決めていたことに対し、当時の小泉純一郎総理が声をかけ、裁判官を入れ、入退院の判断基準に“再犯の恐れ”を入れることになった。ところが実態が変質してきてしまって、“再犯の恐れ”の部分がなくなり、社会復帰だけが目的化してしまった。以前は再犯の恐れがなくなるまできちんとした治療をするということで、より長い治療期間が想定されていたが、それが治安維持のための長期拘禁につながるとして日弁連が猛反対した」と指摘。
また、指定入院医療機関は全国に33病院・833病床あるが、ない県もあり、入院が長期化するケースもある。吉川医師は「北海道や四国はゼロで、北海道のケースで沖縄の医療機関に入院し、社会復帰にうまく繋げられないケースもある。また、家族としては帰ってきて欲しくないと思っているケースもあり、地元に帰ることも難しく、隠れて社会復帰しないといけないケースもある。また、平均の入院期間が1年半となっているのは、非常に短期間で治療しなければならず、医療への重圧もある。多くは未治療なので薬物療法などによって回復はするが、特に大きな事件を起こす方は感情が鈍麻していて慢性の経過が多い。そのような場合は治療が難渋する」と話していた。(AbemaTV/『AbemaPrime』より)