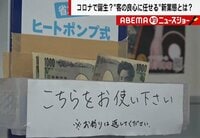サウンドデザイナーの染谷和孝氏は、自らの仕事をそのように形容する。“ウソ”と聞くと人聞き悪いが、染谷氏のウソはご本人曰く“いいウソ”や“気づかれないウソ”である。
「さまざまな音を整理整頓して、皆が抱いているイメージにより近い音を作り上げる。必要に応じて、どうしても抽出できない音をエッセンスとして足していく。一方では削ぎ落すところを削ぎ落す。すべての音を整理整頓することで、より綺麗に、より真に迫って聞こえるようになる。僕らがつくウソとは、そうしたウソです」
染谷氏はこれまで、人気ゲーム『Final Fantasy』シリーズをはじめ映画、CMなどで数多くの作品に音の専門家として携わってきた。そんな染谷氏が今回携わったのが、今月30日から公開される大相撲のドキュメンタリー映画『相撲道~サムライを継ぐ者たち~』である。「武器を持たぬ侍たちのエンターテインメント・ドキュメンタリー」と銘打たれた本作が公開されるのを前に、サウンドデザイナーの職業と本作との関わり、制作の舞台裏などについて話を聞いた。

■「どこまで我慢できるか」がドキュメンタリーの勝負
「普通の音響ではなく、リアリティのある音響をやりたい」というのが、坂田栄治監督からの最初のリクエストだったという。その言葉を聞いた染谷氏の頭には「国技館に限らず相撲を観ているあのシーンをどのようにリアルに伝えられるだろうか」ということだった。また、その他に監督から具体的な指示が無かったことで「逆に僕からどういう提案をできるのかが大事」と気が引き締まったという。
「骨子さえできてしまえば、あとはシーンによって肉付けをすればいい」
染谷氏は、最初の方向性を大事にしている。そのため、制作に入る前に“前哨戦”と名付けた7分ほどの短いクリップを作って監督はじめ、制作陣に提案した。評価は上々だった。この時のことを染谷氏は「僕の方向性を試し、監督の方向性を確認できた」と話し、一つのポイントだったと振り返る。
本作がドキュメンタリーであることも、染谷氏の頭を悩ませた。
「ドキュメンタリーは難しい。音楽やナレーションをたくさん乗せてしまうと、そこでつまらなくなってしまう。どこまで我慢できるかが勝負なんです」
本作では現場の収録をすべて5.1ch以上の素材で撮っていたという。それを最終的にどう活かすかは別にして「相撲部屋の雰囲気をちゃんとしたサラウンドで表現するために用意された素材の広さをどう使っていくか。相撲部屋をあまり広く聞かせてしまうと、国技館の広さが伝わらなくなる。どこが一番広くて、どこが一番狭いか。そういった尺度は大事。実際にロケに行ったりして、観客の入った国技館の音を聞いて、感じたものをそのまま出そうと思った」。
積極的に現場に足を運んだことで、意外な発見もあったという。
「国技館の音は、僕が想像していたそれよりも温かい。国技館、相撲の会場というものは、観客も含めて皆が作っている。贔屓の力士が登場すると皆で盛り上がり、力士ごとに同様のことが展開され、本当にいい雰囲気。アットホームである一方、取組は攻撃的。あの緩急が面白い。そういった雰囲気が出せればという部分は共通していたと思います」

■良いモノに触れてしまった以上、手抜きはできない
一つ課題を乗り越えた染谷氏だったが、また新たな壁にぶつかった。それは「リアルって何だ?」ということだ。
「僕たちが感じているリアルというのは、絶対にウソの世界。実際にマイクをたくさん立ててその場の雰囲気を撮って、それを聞いてもらっても、本当のリアルは皆にとってのリアルとはかけ離れている。皆の心の中で鳴っている『国技館ってすごいな』という音を作らなければいけない。例えば、テレビドラマで電話が鳴るシーンがある。いまの電話の音はもっといい音があるにもかかわらず、固定観念がある。皆の心の中で鳴っている音をどれだけ表現してあげるか。そうすると、結局、ウソをつくことになる。だからこそ、気づかれないウソをつくことが大事なんです」
例えば、館内が沸いたシーン。細かく早いリズムで鳴り響く拍手の中に、一人だけ「パン・パン・パン」と緩慢なリズムの拍手があったとしたら、その音は必要でなくなる。品の無いヤジも然り。そうした必要のないものをすべて整理整頓する。それが染谷氏のいう“いいウソ”だ。
こうした作業を可能にさせるデジタル技術の発展はここ3年、4年のことだというが、じつはこれが気の遠くなるような作業だったと染谷氏はいう。さらに「最初に7分のデモを作った時、この作業はやめようと思ったんです。録音用マイクは何十本とあったので全てに対応していたら、絶対に身体を壊してしまう」と本音も。しかし、そこはプロフェッショナル。「7分のデモを聞いたら『めちゃくちゃよかった』ので、本編でもやるしかないと覚悟を決めました。良いモノを一度見てしまうと、それ以上、クオリティを下げられなくなる。最後は結局、身体を壊して入院したんですけどね(笑)」というオチもついた。
制作は昨年7月から開始され、10月末まで続いた。その間、他の仕事をやることもあったというが、終盤の2週間を染谷氏は病院で過ごすことになった。坂田監督にはLINEで「最後のダビング作業の日程をズラしたい。入院することになりまして…」と伝えたというが、前述の不必要なものを削る作業に膨大な労力を費やしていたこと。さらに初めの段階で「そこまでやったら絶対に倒れるな」という確信がありながら、迷わずにその道を選択していたことなどは、監督はじめ周囲のスタッフの誰にも話していないという。
時間や体力と引き換えに、納得いくものを仕上げたという思いはある。しかし、染谷氏は次のような本音も口にする。
「実際に仕上がってみて、自分が思っているモノが最終的にできたかといえば70%くらい。もうちょっと詰められたという思いは消えません。そのときはベストだけど、1日過ぎると新たな自分がいる。そうなると、もうちょっとこうして、ああしてというのは出てきてしまう」
そんな染谷氏に「作品の中でぜひ、聞いて欲しい音は?」とたずねると「力士がまわしを叩く音や骨と骨がぶつかり合うような立ち合いの音、稽古場での料理の音などはフォーリーと言われる手法で効果音を創って置き換えたりしていますが、やはり国技館の音。そこは僕も含め、チーム皆が相当頑張って創っているので」。そのときにできることはやり切った、そんな清々しい笑顔が返ってきた。
この記事の画像一覧