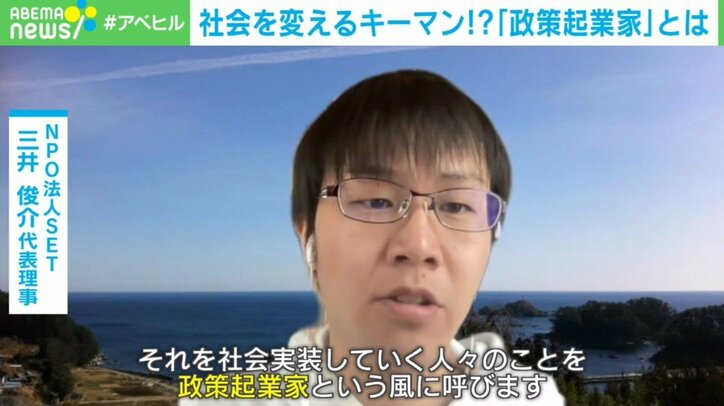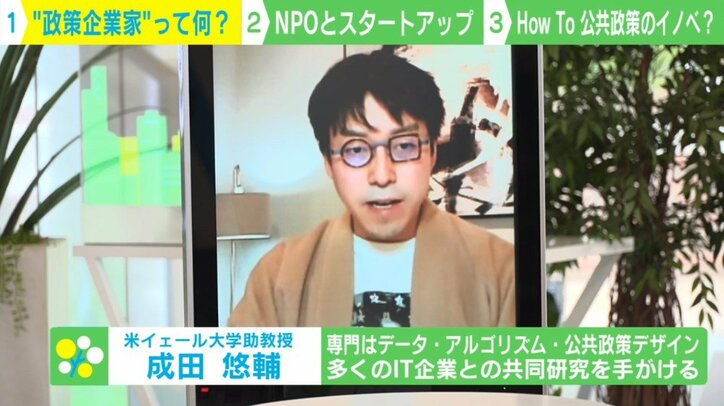社会課題を事業で解決するソーシャルビジネス。一方で、世の中にはビジネスで解決できない社会課題もある。こうした中、先月1冊の本が発売された。
【映像】成田悠輔氏と考える“公共政策のイノベーション”(※解説パート 5分ごろ~)
『政策起業家が社会を変える』(出版:ミネルヴァ書房)――耳慣れない“政策起業家”という存在だが、実は今、世界では彼らが社会を変えるキーマンになると言われている。
「公共政策を革新する、そこにイノベーションを起こすことを促進したり実現したり、それを社会に実装していく人々のことを“政策起業家”と呼ぶ」(NPO法人SET・三井俊介代表理事、以下同)
こう話すのは、NPO法人SETの三井俊介代表理事。日本では数少ない政策起業家の研究者だ。イノベーションを起こし、社会の課題を解決する存在として注目されている“社会起業家”との違いは何か。
「ソーシャルビジネスで解決しようと言っても、現実的にそれができない問題がたくさんある。政策起業家というものにスポットライトを当てることで、行政と協業が進んだり、政策的かつ永続的に解決する仕組みを作ったりすることができる」
三井代表によると、両者の違いは課題解決に対する“アプローチの仕方”だという。社会起業家は、課題解決の主な手段として「ビジネス手法」を重んじる。一方、政策起業家は最終的には「政策変更」を目標とするため、ビジネス手法にこだわるわけではない。
また行政では公平性を重要視する一方、リスクの取りづらさなどから「アプローチしにくい課題も多く存在する」と三井代表は話す。
そんな三井さんも政策起業家の1人。震災後、岩手県陸前高田市で移住定住者を増やす活動をNPOで続けてきた。自治体の受入体制の整備などに課題があった一方で、NPO単体では資金面などに無理があったという。
そこで、三井さんは陸前高田市の市議会議員となり、移住者が生活しやすい環境を作るために政策の提言を行ってきた。
「町が移住定住者を受け入れやすい環境になっているかというと、中々そうはなっていない。市議会議員になってから、一般質問で『そういう環境づくりをしましょう』と何度も取り上げていった」
こうした三井さんの働きかけにより、陸前高田市の移住定住に関わる予算は4年の在職期間で約35倍に。現在は、年間20人ほどが移住してくるようになった。
「僕の中では、(移住定住者を受け入れるための環境づくりは)政策起業に興味を持った原点。政策起業だと思ってやってはいなかったが、振り返ってみるとそのような動きをしていた」
すでに欧米などでは政策起業家という存在が認知され始めている一方、日本ではまだまだ知られておらず、研究なども進んでいない状況だ。多くの人に関心を持ってもらうため、さまざまな発信を行う三井さんに、政策起業家を目指したい人へのアドバイスをもらった。
「大事なのは、行政の皆さんの言語や論理をしっかりと勉強し、リスペクトすること。政策起業といって民間から『よし政策を作ろう』と思っても、行政に『いや、そんなの求めてない』『この人、本当に行政のことをわかっているのかな』と思われては、政策も作りづらい。しっかりと勉強したり、課題は何かを聞いたりする……まずはそういうところからやってみると、後に政策起業へつながると思う」
このニュースについて、米・イェール大学助教授で経済学者の成田悠輔氏に話を聞いた。
――政策起業家とはビジネスでは解決できない多様な社会課題を解決するための公共政策を実現させ、社会変革を促進させる人々のことを指しますが、彼らはそうした“手の届かないところ”を解決するために動いているのでしょうか。
「世の中の問題が多様化している。例えば、Eコマースサイトの提供やオンラインでショッピングができるようにする。これは問題が解決すれば、ビジネスとして成立してお金になる。一方で、子どもの貧困対策やホームレス問題に取り組むことでビジネスとして儲かることはあまりない。“構造的に儲けることは難しいものの、解決することが重要な社会問題”に取り組む起業家のことを政策起業家と呼ぶと思う」
――政策起業家と社会起業家の違いについてはどう考えていますか。
「言葉の違いにこだわりすぎる必要はないが、ここ数十年で日本ではスタートアップやビジネス起業家が増えてきた。その人たちが行ってきた問題解決や世の中への価値の出し方のアプローチを吸収し、そういう人たちから寄付のような形で資金を受けて、スタートアップや起業家との協業やインスピレーションを与え合うといった関係がより蜜になったのが政策起業家なのかな」
――日本では政策起業家という言葉をあまり聞きませんが、アメリカではメジャーなのでしょうか。
「そこそこメジャーだと思う。アメリカには、公立教育や公立学校がうまくいっていない地域が多い。そういった地域で昔ながらの公立学校に頼らずに、新しいタイプの学校を民間で経営していく動きを作り出す運動があった」
――成田さんも起業して公共政策のデジタル化を進めていますが、公共政策のイノベーションには何が大事だと思いますか。
「人材や知識が業界を超えて流れる仕組みを作ることが大事。社会問題に取り組むような政策起業家や社会起業家たちの領域では、お金にならない重要な問題に取り組んでいる人は
“貧しいけれどすごく重要なことをやっている気高い人”というイメージがあると思う。そういう業界とIT業界のようにお金が渦巻く業界では雰囲気や文化も違うし、入ってくる人たちも全然違うのが普通。しかし、この時代で『自治体の仕組みをどうやってデジタル化できるか』ということを考えると、IT業界に勤めているような人たちが社会課題や政策課題に取り組むことが必要になってくる。社会起業のような領域とIT産業の間を人が行き来できるような場所、業界の壁を超えたり穴を作れたりする存在が大事。必要に応じて、異業界の人でチームを組むスタイルがもっと増えるといい」
――なぜ今までは風通しがよくなかったのでしょうか。
「業界ごとに大事だと思っているものが違う。ITビジネスで企業するなら『どこまで稼げたのか』『時価総額はいくらか』が大事。研究者は研究業績で、すごい知識を作り出したことが重要になる。政策起業家は実際に社会問題を解決したり、そのための制度や法律を変えたりすることが大事。全く異なる評価のされ方やインセンティブのために行動しているので、それぞれの業界の凝り固まった仕組みにとらわれずに、『重要な問題を解くためには、使える物は何でも使っていく』という感じで行動する人が増えるといい」
――研究者や政策起業家も、価値観も合わせる必要があるのでしょうか。
「短期的には、合わせるのは難しいと思う。政策起業で突然稼げることはなかなかないし、世の中にとって重要な問題に取り組んだからといって、科学や知識という意味で良いものが作り出せるとは限らない。短期的に重要なのは、人からどう評価されるか、儲かるか、同業者から尊敬されるかを気にしないこと。少し頭のおかしい人たちが増えて、その人たちが人からの評価を気にせずに『この問題に取り組むことが大事だ』と思って勝手に暴走していくといい」
(『ABEMAヒルズ』より)
この記事の画像一覧