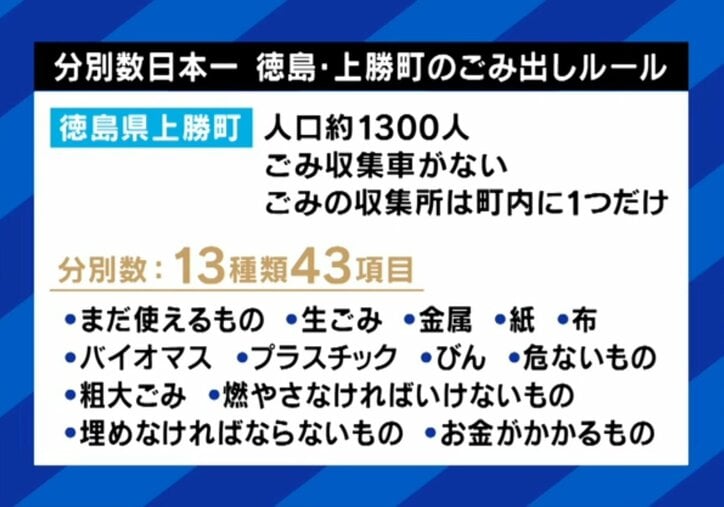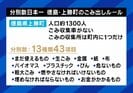■これだけ分けるのは日本だけ?
そもそもは「燃えるごみ」「燃えないごみ」から始まった分別。今では1つの商品を買ったとしても、ごみとして出す場合には、その材質などを確認した上で分別し、さらに自治体によって指定された曜日に合わせて出し分ける必要もある。そもそも、なぜここまで分別が必要になったのか。
廃棄物処理会社に務め、ごみの価値観を変える活動をする「ごみの学校」を立ち上げた寺井正幸氏は「廃棄物処理法ができた時は『燃えるごみ』『燃えないごみ』ということで、燃やすごみを中心に技術や設備投資が進んだ。1990年代に入り、埋め立て処分場がなくなったり、焼却炉の負担が大きくなったりしたので、後からリサイクル法をいろいろ作っていった。結果的に『燃える・燃えない』の上に、法律がどんどん山積みになった。さらに今、リチウムイオンバッテリーのような、焼却炉に入れてはいけない新しい特殊なものも出てきて、より分別が細かくならざるを得なくなってきた」と現状を説明した。
ひろゆき氏からは「パリではリサイクル可能、不可能、ガラスという3種類だけで、後は全部同じごみ。それが工場でAIや機械によって分別される。人間が分別する時に、絶対にミスがなければいいが、間違いは発生する。受け取り側のごみ処理場で必ずもう1回分別するならば、全部工場でやった方がミスも少ないし効率的」だと意見が飛んだ。
これに寺井氏は「その通りだ」と同調しつつ、日本で実施できない理由を述べる。「機械で全部分けられるが理想。ただ日本で廃棄物処理法を立ち上げた時に、各自治体に焼却炉を1基作るという方針を取った。基本的に焼却を中心に全部のインフラやルールが作られている。ヨーロッパは逆にソーティングセンター(混合された廃棄物を、自動選別機を用いて素材別に選別・再資源化する施設)を中心にしたインフラが作られている」と、ごみに関する制度・成り立ちの違いが大きいと説明した。
では今の日本型から欧州型への転換はできないのか。「実際には、品目別に焼却炉から切り替えていくことは、日本の中でも行われていて、家電やプラスチックはいろいろなリサイクル技術を民間企業が開発している。ただ、それぞれ限られた予算の中で設備投資をする方針の中、選別技術でやろうとした自治体が、工場を作って運営するという法律になっていて、自治体にそこまでの財政的な余力がない状況にある」。
さらに法については「もともとの廃棄物処理法が、原則として処理の責任を自治体に義務付けている。自治体の財布の中で個別の投資やルールを決めて運用しろというものだからバラバラになる。1970年の法律が今も変わらずにある状態」と、自治体によって対応がばらつく理由、負担が大きい理由を付け加えた。
■高温で溶かす「溶融炉」のメリット・デメリットは