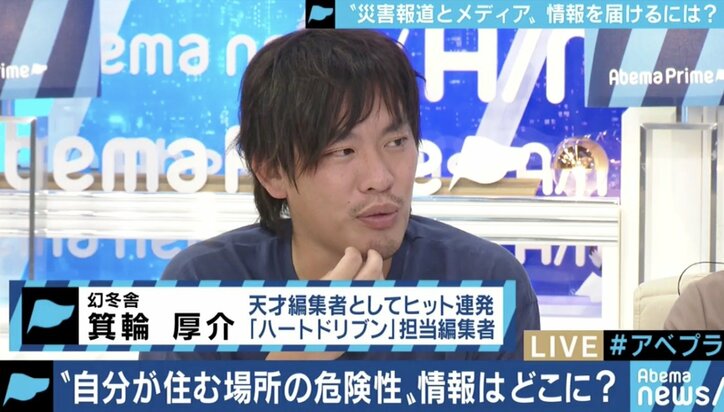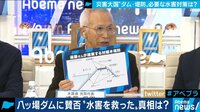国土交通省は15日、台風19号で堤防が決壊した河川が全国7県の52河川、73か所に上ったことを明らかにした。避難勧告や避難指示などの情報が配信されるエリアメールや自治体によるSNS、そしてハザードマップの活用について、AbemaTV『AbemaPrime』では議論した。
まず、避難者や被災者についての情報収集やニーズ把握のため、自治体も情報通信技術をどう活用するのか、今回も課題が浮き彫りになった。長野県が運用するアカウント「長野県防災」(@BosaiNaganoPref)では、「捜索隊による救助活動を実施します!捜索隊も皆様を全力で探し、救助するため全身全霊をかけて活動しています。ご自宅や施設等で救助を待たれている皆さん、大丈夫です!必ず助けに行きます!」と呼びかけるとともに、県民の情報収集のためのリンクをツイートするなどしている。
自民党の小林史明衆議院議員は「今は家の壁も厚くなっているし、雨が降っていれば避難を呼びかける自治体の防災無線が聞こえにくい。 こういうときに手元の携帯電話にプッシュ型の通知ができると良いだろうし、SNSで自分がどこにいるかなどを発信できるのもいい。その意味で、長野県の使い方は大変良い。救助してほしい人がハッシュタグを付けて投稿、防災ヘリが救助に行くということを通知し、実際に駆けつけた実例もある。こういうことは全ての県がやれた方がいいし、災害時にSNSを使うのかということを、普段から行政と民間、国民の皆さんで想定を整理しておく必要があると思う」と話す。また、釜石市地方創生アドバイザーの藤沢烈氏は「自治体でツイッターを活用しているのは6割程度と言われている。フェイクニュースがあったとしても、オフィシャルなアカウントが打ち消すこともできる」とした。
幻冬舎の編集者・箕輪厚介氏は「もし僕がTwitterをやっていないか、もしくは使えない状態だったとしたら不安だったと思う。災害の現場から投稿される情報はとても有効だ。それなのに国や自治体が活用することについては"できる人がやればいい"というような段階で止まっているのは怠慢だと思う。不確かな情報も投稿されているからこそ、信頼できるオフィシャルな機関がやるべきだ」、カンニング竹山も「できる人が行政にいるかいないかで違うと思うので、国が全国で教育していくということをやらなければ、地域格差が生まれそうな気がする」と指摘した。
小林議員は「ご指摘はその通りだ。今の災害対策の仕組みは基本的に自治体に責任があることになっていて、先日の千葉の災害の場合も、地域から情報が上がって来なかったので国が対応できなかった。だとすれば、国側から情報を取りにいくということが基本になっていれば、もっと早く対応できるということだ。SNSでの発信も国側でハッシュタグを決めて、やり方も整理して、研修もするというようにやっていった方がいいと思う。自民党青年局でも、各県にいる地方議員の仲間とSNSの使い方の研修会を全国やる予定だ」
一方、慶應義塾大学特別招聘教授の夏野剛氏は「もっと深刻なのは電力会社だ。軽井沢に滞在中に停電に遭ったが、ホームページに細かい情報を出していなかった。電気はインフラとしてものすごく大事で、あれだけの原発事故を起こし、最近は関電の話もあったわけで、本当に民間にまかせておいていいのかという本気で思う。あるいは道路の情報も足りず、通行止めになっているのを見ては引き返し、いわば手探りで東京に戻ってきた。鉄道もJRが出している情報よりもTwitterで検索したほうが早いケースもある。3.11のときに自動車会社が通行可能な道路のマップを提供していたが、こういうことこそ、民間と国でやらなければならないと思う。あれから8年も経っているのに、何も変わってない。それは公務員が終身雇用で、若い職員を雇っていないからだ。一方で、国が全て統一しようとすると悪い方向に行く場合もある。長野県のツイートの"全身全霊で"というような表現も、国が標準化しようとすると"個人の感情だから入れちゃだめだ"とか言われてしまうかもしれない(笑)」。
■「どれだけの人がハザードマップを見ているか」
また、カンニング竹山は「ハザードマップという言葉が出てきた当初は"何だそれ?"と思っていたが、色々なところで災害が起きた後、"ハザードマップ通りだった"ということが増えた。自治体が作っているハザードマップの信頼性はどんどん高まっている」とコメント。一方、夏野氏は「フォーマットはバラバラかもしれないが、"土地の値段が下がる"等、ものすごい反対の中、自治体はいいことをしたと思う。しかし、どれだけの人がハザードマップを見ているかということだ。確かに住んでいる場所が黄色や赤になっているのを見るのは嫌かもしれないが、浸水するところは次も浸水する。そして申し訳ないが、今回浸水した地域のほとんどはハザードマップで危険な地域だった。これから人口が減少する中、各地域で土木工事を行ってなんとかするという時代は終わった。もう日本にそんな財力はない。"先祖代々住んでいます"ということよりも命が大事だという意識改革をしないと、これから災害が激甚化していく中、危険は増していく。そして次に対応しないといけないのは、不動産取引の際にハザードマップの情報を提示することの義務付けだ。知らないで借りたら危ないところだった、という人も多いし、事前に知っていれば、危機意識も違うと思う」と提言した。
これに対して箕輪氏は「あらかじめリスクを承知した上で住むという判断をするのが健全だと思う。ただし仮に僕の住んでいるエリアが対象になっていたとしても、現実には動くことはできなかったと思う。"大丈夫でしょ"と思ってしまう自分がいるし、"命を最優先にしてください"と言われても、その最優先が避難なのか、それとも動かないでいることなのかの判断基準を持っていない。その辺のトレーニングの機会もないところが問題だ」、テレビ朝日の平石直之アナは「地域によってはエリアメールもどんどん配信されてきたと思うが、気象庁の発表には"命を守る行動を"、"数十年に一度"といった強い言葉が並ぶし、我々の原稿にもそれらが入る。じゃあどうすればいいかが大事なのに、どうしても"丸投げ感が出てしまう」と懸念を示した。
藤沢氏は「改めてハザードマップの重要性が認識されたと思う。ただ、地方と都市部で使われ方がかなり違ったのではないか。東京では何となく"危険"としか書かれていないが、例えば釜石市では地域でワークショップを重ねていて、"どういう状況になったら避難するのか"という情報まで盛り込まれていて、住民の方もよくわかっている。都市部でこうしたことを実現させるのは簡単ではないと思うが、これから災害は増えると思うし、残された課題だ」と指摘した。小林議員は「ハザードマップとその活用の共通化、標準化というものを改めて考えなければいけない。今回、自治体のサイトにアクセスが集中して情報が見られなくなった問題もある。現状では自治体ごとにサイトとサーバーを持っているので、アクセスが集中すると落ちてしまう。これを国全体で共有しておけば、そのようなリスクは下がる。ハザードマップに関しても、私の地元は広島県の福山市だが、去年7月に西日本豪雨災害に遭い、私自身も被災した。市の道路情報は、"〇〇交差点通行止め"と文字で書いてあり、県の方は県道の通行止め情報が、そして国のホームページには高速道路と国道だけが載っていた。国民からすれば利便性が低すぎる。こういうものは一箇所にまとめておくべきだし、改めて国で共通化するものと、自治体ごとに任せるものを再整理することが必要だ」と話していた。(AbemaTV/『AbemaPrime』より)