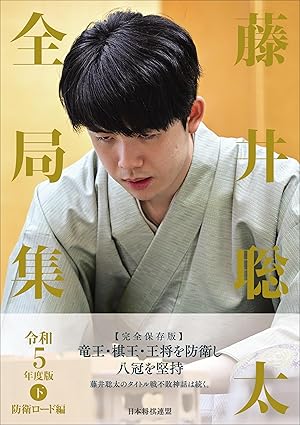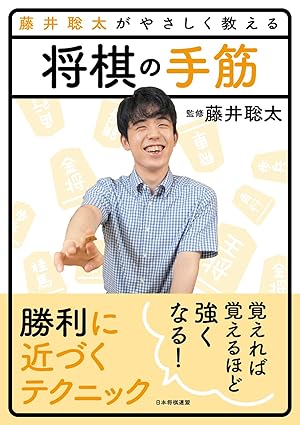「将棋」「詰将棋」「藤井」と聞くと最近ではデビュー以来、記録ラッシュを続けている藤井聡太竜王(王位、叡王、棋聖、19)を想像するファンも多いだろうが“元祖・藤井”とも言われる藤井猛九段(51)も、詰将棋に対して熱い思いを持っている。振り飛車のオリジナル戦術「藤井システム」が将棋界ではあまりに有名だが、今年初めて使ったTwitterを機に、詰将棋熱が再燃。放送対局出演時に、20分近くノンストップで語り続けた。ここでは、その一部を紹介する。
【動画】藤井猛九段、詰将棋への思いを語る(4時間31分ごろ~)
(女流ABEMAトーナメント「チーム西山」で運営したTwitterアカウントで詰将棋を投稿したことについて)
私、昔は結構詰将棋を作る機会が多かったんですよ。ひっそりとね。雑誌のコーナーもあったりしたので、作ったこともあったんです。(Twitterでは)最初は解きやすい7手詰を出したんです。その後、西山朋佳さん(女流二冠)がタイトルを取ったんで、西山さんに向けてというのであれば難しくていいかなと。難しい詰将棋って出すところがないんですよ。アマチュアの方に解いてくださいというのも15手詰ぐらいが限界。たまに20何手のものができても、出すところがない。とはいえ、なんか出したいじゃない。だから西山さんに向けて出したんです。
(詰将棋制作について)
1回、難しいのを出しちゃったら、簡単なのには戻れないんですよ。1回、飛車と角がいるだけで、ただ成香で追いかけていくのを出したら好評で「手数が長くても解けた」と。それで調子に乗っちゃった。手数は17手詰なんだけど、成香が動くだけ。「17手詰を解いたの初めて」という方もいらっしゃった。そこから詰将棋に興味を持ってくれたらいいじゃないですか。難しい15手詰よりも、長い70手詰の方がいいんだよ。1回65手詰出してみたんだよ。そういうの好きでね。スポーツに例えたら、遠投なんですよね。キャッチボールより、遠くに投げるってあるじゃないですか。単純な作業なんだけど、遠くに投げるトレーニングと、長編の詰将棋は同じなんです。5手詰はキャッチボール、65手詰は肩を鍛える。(難易度が)解ける範囲だったら、手数は長くても関係ないんですよ。65手詰を出して、初めて解けたという人もいるわけだから。
(自身の詰将棋への思い)
奨励会に入るまでは、30手詰も解いたことはなかったですよ。江戸時代の詰将棋を解かないとダメだと言われていたので、奨励会に入って、やったほうがいいなと。最初はうわーっと思いましたよ。「無理でしょ、こんなの」と(苦笑)。でも、やっているうちに解けるんですよ。やらないとダメですね。やると自信になる。慣れてしまえば、どれだけ長くても関係ないです。奨励会入って、30手超えの詰将棋を解くようになって、読みの力がついたんです。最近の若手、詰将棋やらないイメージなんだよね。すごい好きか、全然興味ないか、どっちか。
(長編詰将棋の魅力)
長いのは、解くと感動するんですよ。江戸時代の有名なやつとか「すげえ」と。美しいですよ、作品として。形にこだわったのと、難解さにこだわったのと、2種類あるんですよ。プロは別として、アマチュアの方は詰将棋嫌いですよね。なんで嫌いかって言ったら、難しいからですよ。だから簡単ならいいわけです。やってみて解けなかったら、むしろ解ける問題に(レベルを)落とした方がいいね。3手詰がちょうどいい人もいれば、段階だからね。長くなるほど、簡単な要素が多いと思うんですよ。ただただ玉がぐるぐる動くだけだから。
(詰将棋制作のおもしろさ)
Twitter用に詰将棋を考えているうちに、手数を伸ばしちゃったんですよ。僕は長編詰将棋が好きで、昔は詰将棋パラダイスを解いていたんですけど。自分の詰将棋が完成すると、ちょっと気の利いた手筋が浮かんだと思った時に、似たような詰将棋を解いたことがあるって気がつくんですよ。「あれ?」みたいな。自分の力で発見したように思えた筋が、「絶対過去にこれ解いてるよ」と。そういう気持ちに襲われる。そういうの、どうすればいいんですかね(苦笑)。絶対、過去の記憶の中から出てきただけと気がつくことがありますね。どうしても似通っちゃうのはしょうがないですね。誰かの作品の一部分と類似しちゃう。作ってみると、作る人の苦労ってわかりますね。たいがい、詰将棋は解くだけじゃないですか。解けて「どうだ!」って感じ。ここに作者の苦労があるんだとか、あんまり考えないですよね。でも作る方は、そういうところが一番大変なんですよ。
(ABEMA/将棋チャンネルより)