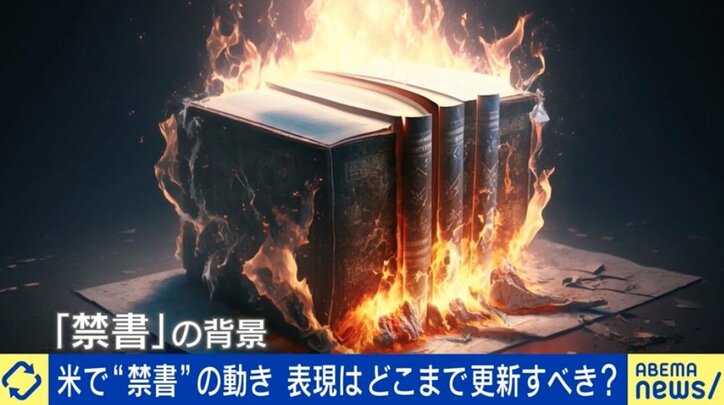「本を禁止する行為に対し、私たちは反対すべきだ」という異例の呼びかけ。南部フロリダ州の公立学校で、ある詩が閲覧制限の対象になったことを受けてアメリカ・ホワイトハウスが行ったものだ。
【映像】『かちかち山』狸がおばあさんを殺し「婆汁」に→「今」の形は?
対象となったのが、アマンダ・ゴーマン氏の詩『私たちの登る丘』。バイデン大統領の就任式でも朗読された作品で、全ての文化や人種、肌の色を認め合って歩んでいこうという内容だ。しかし、閲覧制限を申し立てている保護者は「間接的に憎悪を含んでいる。児童を洗脳する」と訴えている。
出版に対する論争はこれだけではない。ミステリーの女王と言われるアガサ・クリスティの作品など、古くからある名作文学に対しても現代に合わせて差別的と思える表現を削除したり、現代風に改編して絶版を逃れようとする動きも進んでいる。
アメリカで進む禁書の動きの背景、そして、時代に合わせた表現の必要性について、『ABEMA Prime』で専門家と共に考えた。
◼︎ノーベル文学賞作家の作品も禁書に
作家団体「ペン・アメリカ」の報告書によると、2022年6月までの1年間で「禁書」に選ばれ、公立学校・図書館から撤去された本は1648タイトルあるという(書店での購入は可能)。
『風と共に去りぬ』などの翻訳を行いアメリカで進む禁書の問題点を指摘している翻訳家の鴻巣友季子氏は「1つはセックスが入っているもの。それからジェンダーにまつわるもので、特にLGBTQと言われる性的少数者の題材。そして人種に関わる本が、この10年くらい一貫して撤去リクエストを受けやすい」と説明。
禁書扱いとなった『青い眼がほしい』『ビラヴド』は、黒人への虐待やレイプ被害が描かれた小説だ。鴻巣氏は「読ませないのは『歴史の隠蔽』に当たる。実際、ここに書かれている通りか、それよりもひどい虐待を黒人は受けてきた。『ビラヴド』は逃亡奴隷の話で、現実にあった幼児殺害事件をもとに書かれていて、そういう歴史の暗黒部のようなものを読む権利はある」と話す。
一方で、「白人側にも、自分たちがアメリカを正しい国として作り上げてきたという自負がある。そこで『あなたたちがやったのはとてもひどいことだった』と言われると、自分たちの子どもは傷つくだろう。親心から『うちの子には読ませたくない』という気持ちも分からなくはない」と述べた。
「差別表現のない文学はきれいごとだ」との意見を持つ、作家で「ユニークフェイス研究所」代表の石井政之氏は「僕は生まれつき顔に痣があることをテーマに出版活動をしていた。マイノリティや今まで声をあげられなかった人たちが表現活動をするのは本当に大事なことで、アメリカでも日本でも保障されないといけない。そして、子どもの時に社会の理不尽さをしっかりと伝えていくことこそが、大きな意味での人権教育になると思う。そこで過去のマイノリティな作家の才能に触れることはとても大事だ」と話した。
◼︎禁書にすれば選挙で勝てる?
さらに、鴻巣氏は「選挙活動・政治活動に絡み合っている」とも指摘する。
「今アメリカは共和党と民主党、保守とリベラルの分断が深いと言われているが、要するにこれは『図書館を舞台にした代理戦争』のようなものだ。去年の中間選挙もこの“有害図書撤去問題”が一つの大きな争点になった。そこで人気を取れた、ろくに政治経験のない人が当選したりしている、来年は大統領選挙があるので、票取りという意味合いは大いにある。
やはりリベラルに対する大きな反動の一環なんだと思う。LGBTQや妊娠中絶手術の是非は、今大きくアメリカを真っ二つにしている争点。これらに関する本自体の良し悪しではなくて、“このコマを取ると、どの人たちを賛成者として引っ張ってこられるか”という考えで行われている。『青い眼が欲しい』をろくに読んでもいない人が批判しているんだと思う」
◼︎アガサ・クリスティの名作を“現代風”にいじる?
禁書以外にも、アメリカだけでなくヨーロッパも含めて「名作の改訂」が出版業界で論争になっている。例えば『チャーリーとチョコレート工場』原作の「太った」という表現が「巨大」に変えられたり(批判を受けて修正撤回)、『アッホ夫婦』では「醜くて野獣のよう」の「醜くて」という表現が削られたりしている。
こうした流れに石井氏は「原作者の表現の力をそぎ落とすだけだ。そもそも“現代風”を定義するのは誰なのか。『差別はよくない』と言っている人たちも同じ人間であり、やはり誰かを差別しているはず。だから、戦争も起きているわけで、その理不尽さの中で出てくる表現が書かれるのは当然だ」と指摘。
鴻巣氏は同意しつつ、「今はキャンセル運動がものすごく激しい。言葉一つとられて『これはレイシズムだ。差別だ』と言われ、絶版まで追い込まれる可能性もある。古典名作というのは、購買者が一定数途切れずに長年来て、テレビ、ラジオ、関連商品などの収益ルートがあり、雇用機会も生んでいる。たくさんの人を食わせているという面があるので、出版社が(改訂という)守りに入ってしまう」と説明した。
石井氏は「人権という意識が芽生えていなかった時代、日本でもヨーロッパでも、気に入らない人間を見たら殺すということは普通に起きていた。だからこそ、村人は武装して家族を守っていたわけで、そういう野蛮な時代はやはり書き残されなければいけない。形を変えて今、日本でも海外でもその野蛮さは残っており、表現者が文章を書いて作品にしている中で、現代風に書き直すのは本当に無駄な作業だと思う」と苦言を呈した。
(『ABEMA Prime』より)