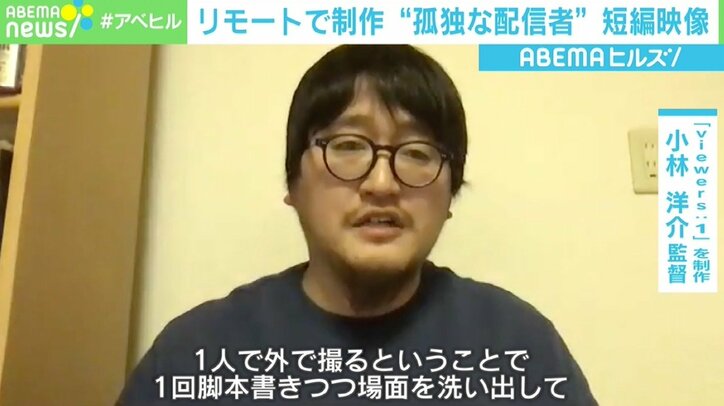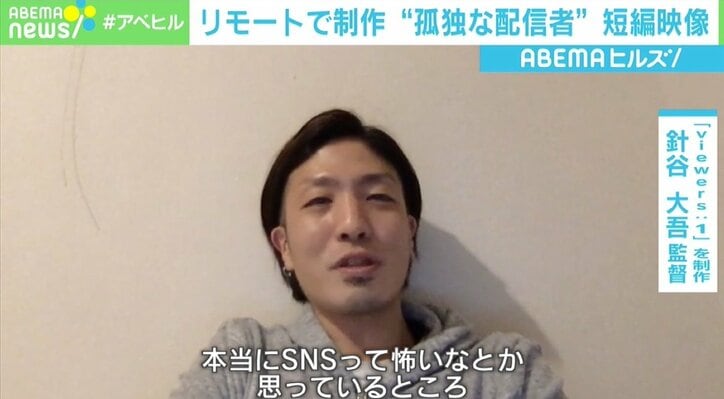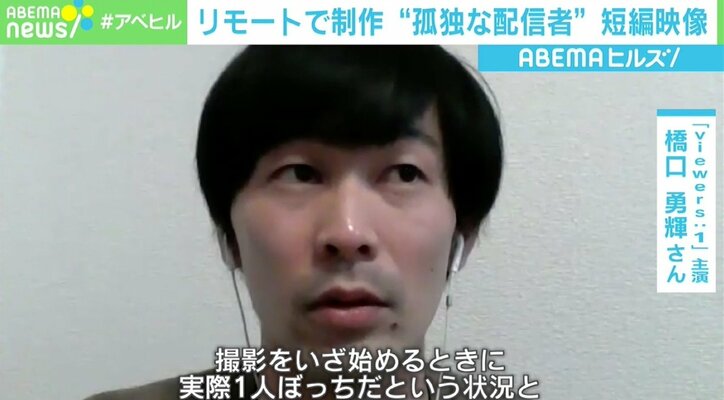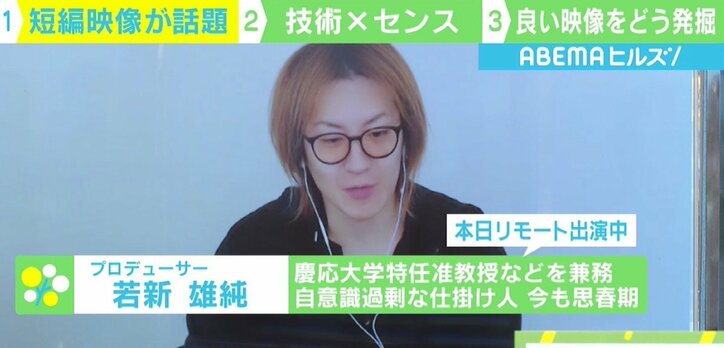「これまじですごいんだけど、なんで再生数500いってないの? ちょっとせめて私のフォロワーには見てもらいたい」
この数日、SNSで“ある動画”に関する数々の感想が投稿され、注目が集まっている。クリエイター発掘プロジェクト、ジェムストーンが開催したショートフィルムコンテストのグランプリ作品「viewers:1」だ。6回目の開催となる今回は、企画から撮影まで全ての過程において、リモートで作られた映像がテーマだという。
【映像】口コミで話題の140秒動画 “人類滅亡後の配信者”「viewers:1」
人一人いない世界で、スマートフォンを手に配信する男性。孤独な実況中継を続ける中、衝撃のラストシーンを迎える。“人類滅亡後の配信者”の世界を見事に描いたこの動画は、去年12月に公開され、先週金曜日、ついにグランプリを受賞。最初は数百回しか再生されていなかったものの、Twitter上で次々と感想が広がり、視聴回数が急増。今では40万回再生を超えている(※数字は2月3日時点)。
ニュース番組「ABEMAヒルズ」では作品の裏側について、制作を担当した監督の小林洋介さん、針谷大吾さん、主演の橋口勇輝さんを取材。
監督の小林洋介さんは「(反響は)全く想像していなかったです。正直まだ混乱しているというか、これはどういうことなんだっけという感じです」と語る。撮影に関しては、基本的に主演の橋口さん1人で、入念な準備をリモートで行ったという。
「1人で外で撮るということで、1回脚本を書きつつ、場面を洗い出しました。Googleマップなどで1回ロケハンして、1回見に行って、そこで実際『こういうアングルで、これくらいのお芝居をするならここかな』というのを全部決めた。その上で役者の橋口君とZoomでひたすら芝居のリハーサルをした。しゃべりの構成、セリフのスピード感も事前にある程度固めて、撮影に臨んだ」(小林洋介さん)
また、劇中のロボットはCGではないという。
「あれはけっこう3Dで作っているように思ってくれる人が多くてうれしいのですが、意外と雑で、全部写真なんです。家の掃除機や炊飯器、家電の写真とその辺の工事現場の重機の写真など、あといろいろ細かい文具のさきっちょとかの写真を使っています」
SNSで注目されたのが、本格的なSF映画のような映像のクオリティだ。意外にも、リモートでできることを駆使し、そこまで大掛かりな技術は使っていないという。
共に制作を担当した針谷大吾さんは「『そこをそういう風に思うんですね』というところがあったり、『これ伝わらないんだろうな」と思いながら適当にやったところが意外と伝わっていたりした。本当にSNSって怖いなとか思っているところです」と語る。
そして、孤独な配信者を演じた、俳優の橋口勇輝さんは「撮影をいざ始めるときに、実際1人ぼっちだという状況と、でも誰かが見てくれていると信じていることが、役柄とかすかにリンクしていた」と話す。その上で「ただ、それを最後の最後にこらえきれなくなる瞬間というのは、自分でもやっていて何かくるものもありましたし、表現することができたかなと自負しております」と手応えをコメント。
「本当に今となっては(再生数が)こんなに大きな数字になりましたが、最初は本当にある方が『この動画を見てほしい』という風に発信していただいて、それを受け取った人たちがどんどん広げていただいた。みなさんが見ていただいたことと、それをよりいろいろな方に勧めていただいたこと、今も見ていただいていること、何度も繰り返し見ていただいている方もいらっしゃると思うので、本当に感謝してます」(橋口勇輝さん)
■若新雄純氏「技術とセンスが結びついて新しい作品が生まれている」
この“人類滅亡後の配信者”の動画に、慶応大学特任准教授などを務めるプロデューサーの若新雄純氏は「面白い解釈、卓越した私見でハイレベルなセンスによって作られているなと思った」と評価する。
「他の入賞作品もいくつか見させてもらったが、ずっと家の中だけでやる動画や電子タブレットを使った動画など、(テーマである)リモートを解釈すると普通はそうなる。このグランプリを受賞した作品は、誰とも直接会わない、というリモート社会のもう一つの側面。リアルに対面せず、ずっと自撮りしている」(以下、若新雄純氏)
また、若新氏は“自撮り”が作品の世界観に大きく影響していると指摘。
「自撮りは簡易的な撮影手法で、固定カメラがあったり、別の音響スタッフがいたり充実した撮影環境というわけではない。だが、手軽な自撮りで完結していることそのものが、物語の世界観を作っている。そこに気づくことが難しい。いろいろな技術が安く手に入るようになってきたが、人々のセンスが追いついているかというと、まだ誰もが技術を使いこなせるほどセンスを持っているわけじゃない。技術と卓越したセンスが結びついて、現代の新しい作品が生まれている」
YouTubeなど動画サイトの台頭により、誰しもが動画を発信できるようになった現代。若新氏は「投稿する側からすると、気づいてもらいにくくなっている」と指摘する。
「1つの画面を見ていると気づかないだけで、YouTubeの世界は日に日に投稿される動画が増えている。テレビの世界ならリモコンにボタンが増えていっても、物理的に限界があるが、YouTubeではチャンネル数が増えていけばいくほど、気づいてもらいにくくなる。誰でも配信者、クリエイターになれると言われているが、その一方で、配信者が増えるほど気づいてもらいにくくなる。今回は偶然発掘された動画かもしれないが、広めるべき動画が埋もれていかないよう、広まっていく仕組みを考えないといけない」
(ABEMA/「ABEMAヒルズ」より)
この記事の画像一覧