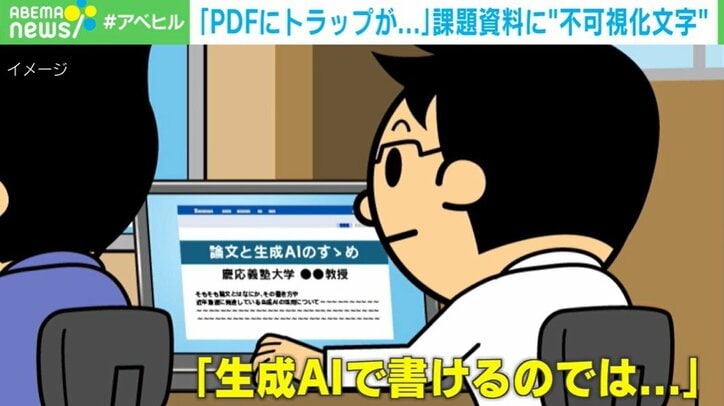生成AIのハルシネーションなどが問題となる中、慶應大学の新入生向けの授業で行った注意喚起の方法が画期的だと話題になった。
【映像】「不可視化文章」が隠されたPDF(実際に読み込ませた様子)
現役の学生によると、この授業は論文の書き方や生成AIの活用に関するもので、使われたスライドのPDFファイルが学生に配布されたうえで、授業の感想を書くという課題が課せられたという。
「スライドがあるなら、生成AIに読み込ませればいい」と思うところだが、このPDFには教員による工夫が施されていたとみられている。
「私も最初楽しようと思って、AIに読み込ませた。すると、とんちんかんなアウトプットが出てきた。実際のスライドと見比べてみて、何かおかしいなと」(慶應大学環境情報学部1年 Taiseiさん、以下同)
生成AIから、授業とは関係のない文章が出力されることに気付いたTaiseiさん。結局、課題はすべて自力で書いて提出したが、その後、無関係の内容が含まれた感想を提出した学生が一定数いたことや、そうした学生は評価対象外とするといった内容のメールが届いたという。
「感想を書くうえでPDFをそのまま読み込ませると、人間には目視できない文字列が、AIだとそれを認識して、全く違う文章が生成されるというトラップみたいなものが仕掛けられていた」
このPDFに隠されていたのが、ぱっと見ただけでは確認できないいわゆる「不可視化文字」による文章だったという。
今回の授業や課題の意図について、大学側はこうコメントしている。
「多様な学問分野の基礎的な知識や思考法の習得と併せて、生成AIをはじめとする最新テクノロジーにより急速に変化する教育環境の中で、不用意な技術利用がもたらすリスクについて学生自身が深く理解することを目指しております。課題では生成AIの信頼性を見直し、出力を批判的に考察する力を養うことを目的としました。本取り組みは授業の一環として実施しており、学生の学びを大切にする観点から、教育効果を考慮して詳細のご説明は差し控えさせていただきます」(慶應大学のコメント)
今回の授業で、論文の書き方だけでなく、生成AIの仕組みや、利用上の注意点について身をもって学んだTaiseiさんは以下のように述べる。
「AIが当たり前になってきている世の中で、でもやっぱりAIを学ぶ機会っていうのはそんな多くないわけで。実際にこういう、怖さというのを直接的に教えられたのはとてもいい教育なんじゃないか。こういうユニークな発想が出てくるのも、教授がこういう発想をしてくれるのも面白いし、こっちもだまされたっていう悔しさもあって、こういう発想ができるようになりたいなと思った」
今後、論点となりそうな点は?「それ自体リスクがあること」