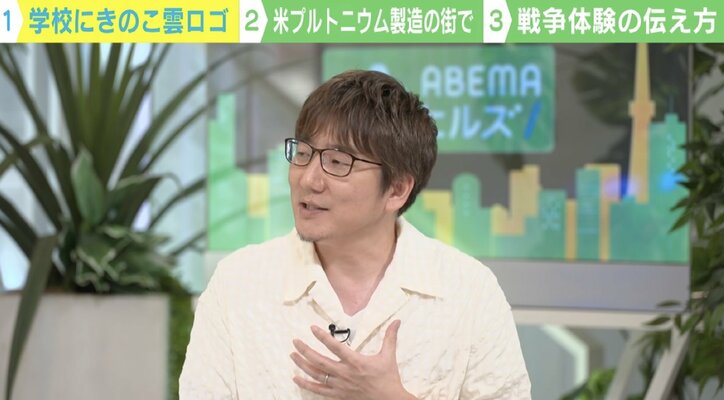2022年に公開された「あのプラタナスの木のように」。カメラは6歳のときに広島で被爆した後東利治さんに密着。後東さんはこれまで“あの日”のことを口にしてこなかった。
「(子どもに被爆の話をしたことは)全然ない。伝えたくない。実際に身近にそういう体験をした人は話したくないんじゃないかと思う」
そんな後東さんが胸の内にしまっていた“あの日の記憶”について話すドキュメンタリー。出演するきっかけになったのは、広島に縁もゆかりもなかったこの作品の制作者だ。
早稲田大学に通う古賀野々華さん(23)。現在は大学で原爆の被害と加害の構造などを研究しながら、大学外でドキュメンタリー制作や被爆者との対話を行っている。
福岡県出身の古賀さん。被爆地出身でもなければ、被爆者の家族でもない。彼女の“原点”となったのは高校時代の留学だった。
街のいたるところに掲げられたキノコ雲のイラスト。彼女が留学したのは、アメリカのワシントン州リッチランド。留学したリッチランド高校もキノコ雲のモチーフが学校のロゴとして体育館や壁やパーカーなど様々な場所で使用されていたという。
街のすぐ近くには、第二次世界大戦中に設立された「ハンフォード核施設」があり、ここで作られたプルトニウムを積んだ原子爆弾が長崎に投下された。
「街の人たちは、原爆が戦争を終わらせたと信じ、自分たちが原爆を作ったことに誇りを持っていた。(学校では原爆についての)授業は一度もなく、根拠もなく誇りに思っている感じがした。自分たちの歴史を学ぶ機会もなければ、長崎に落とされた原爆の惨状や犠牲者の数を学ぶ機会も全くなかった」(古賀さん)
黙ってはいられなかった。留学生としての意義を感じた古賀さんは、被爆国の気持ちや被爆者の存在を伝えるため、校内でスピーチを行った。
自身にとってキノコ雲は犠牲者や平和を心に刻むもの。長崎に投下された原爆の当初の目標は福岡だったことから「天気次第で自分はこの世にいなかった」といえる。
スピーチ後、「日本側の視点は知らなかったからありがとう」という声を聞いた。
古賀さんの勇気は被爆者の心を動かす。その言葉は広島新聞にも掲載され、その記事を読んだ後東利治さんが「自分も何か被爆者として広島で頑張りたい」と彼女に手紙を送ってきたのだ。
そして2022年、ドキュメンタリーの制作がスタート。古賀さんのカメラの前で、後東さんは“あの日”のことを話し始めた。
「自分だけ生き残って悪いなという気持ちがある。複雑だ」(後東さん)
「(被爆者の方と話すのは)初めてで、言葉にならない感情があった。被爆の体験は壮絶でどうしても自分の中に落とし込むことが難しい。ただただ頷いて聞くことしかできなかった」(古賀さん)
ドキュメンタリー制作後、古賀さんは再びリッチランドへ。「日米の原爆への認識の違いを深く調べたい」。そんな思いからだった。
「現地の人の話で心に残ったのは、『僕の弟が第二次世界大戦中に日本に行く準備をしていたが、原爆が落とされて戦争が終わったので助かった』という声。日本は原爆を落とされて被爆者の苦しみがある一方、アメリカのリッチランドには『自分たちが頑張ったおかげでアメリカが戦争に勝った』という正義がある」(古賀さん)
一方、核施設の影響による住民の健康被害など、リッチランドで今も核に苦しむ人の存在も知った。大学卒業後はジャーナリストの道を目指し、原爆に対する答えを追い続けている。
そんな古賀さんに「継承」と「これからの核」について考えを尋ねた。
古賀さんは「後東さんや被爆者の話を聞いたことで、私の中に培われた倫理観がある。その視点でアメリカの被ばく者に今後どう寄り添っていくか。ジャーナリストは何かを伝える仕事だが、常に誰のために伝えるのかを考えられるジャーナリストになりたい」と答えた。
山田進太郎D&I財団 COOの石倉秀明氏は「原爆体験の継承」と「日本が果たすべき役割」について次のように述べた。
「僕は小学生の頃に『はだしのゲン』や『火垂るの墓』を見て『本当に怖い』と感じた。“生々しいが故に心に残るリアリティ”や共通認識を体験談や作品などを通して日本の中でどう受け継ぎ、そしてアニメのように日本が得意な分野も使って、世界にどう伝えるかを考えるべきだ」
「一方で今、核を持つ国がたくさんあり、一気にはなくせないという現実があるとすると、核を持つ国に誤った判断をさせないために日本に何ができるのか、メッセージの発信の仕方など、戦略的な動きも必要なのではないか。また、被爆国である日本と、かつて核を使ったアメリカだからこそわかる、この判断が良くないことで、それを仕組みとしてさせないためにどうするかというメッセージをうまく伝えていく方法をもっと考えていくべきだ。リッチランドの人々も、核を作りたくて作ったというよりは当時は仕事として国の政策のもとに行われたことだろう。『間違った判断』をさせないために、いかにシステム、政治の仕組みに落とし込むかということが重要になるのではないか」
(『ABEMAヒルズ』より)