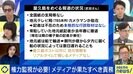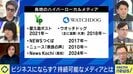■「各国でも儲けてない」ものの、メリットも? 持続可能性は
同志社大学大学院教授で、主に滋賀・大津のことを扱う「ウオッチドッグ」デスクの小黒純氏。ハイパーローカルメディアについて、「まだ日本では馴染みがない言葉だと思うが、欧米ではかなり前からキーワードになっている。地域に根ざして社会問題を掘り起こし、行政、さらには地元の権力を監視することだ」と説明。
収益面については、「非営利が基本かなと思う。ビジネスモデルまで至らないし、各国でもそこで大儲けしている状況にはない」とするが、現代ならではのメリットもあると話す。
「逆に言えば、お金をかけないでやっていくことができる時代になっていると思う。もちろん何らかの費用はかかり、それを本業にして生活を立てるのは難しいかもしれない。ただ、新聞を紙で印刷して配らなくても、Webでは瞬時に伝えることができるし、これまで伝えたものをアーカイブ化できる。そうすれば、どれだけ事実に根づいたものを報じているか、どれだけの積み重ねがあるか、は一目瞭然だ。そこがメディアの信頼性につながるのではないか」
持続性について、武田氏は「私が腹をくくって頑張らなければいけないのが1つ。それから、ここ10年ぐらい屋久島町と対峙してきたノウハウがあり、それを今ノンフィクションにまとめている。本筋の報道では収入が得られないが、本や雑誌に書くというプラスアルファの仕事ができる段階に来ている。徐々に活動と収入の幅を広げて、持続可能なかたちにできればと思っている」との見立てを示した。(『ABEMA Prime』より)
この記事の画像一覧