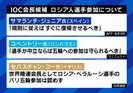「国の代表」「国の威信をかけて」、いわば愛国心を示すものにもなっているオリンピックだが、それもまた転換期を迎えていると渡辺氏は語る。「ロシアの体操選手は3歳くらいから始めている。なんで体操を続けるかと言えば、お母さんが喜ぶから、コーチが喜ぶから、見ている人が喜ぶから、応援してくれる人がたくさんいるからだ。ところがある日、突然ステイト(政府)が来て『お前は国のために戦わなければいけない。国のためにメダルを取らなければいけない』とプレッシャーをかけられる。何のためのスポーツなのか。おかしいんじゃないかと、ロシアのメディアにも敢えて言った。そういった在り方、考え方も変えていかないといけない」。
渡辺氏は近年、五輪種目に採用されたスケートボードやBMXなどを例に挙げると「アーバンスポーツ(都市を舞台に、音楽やファッションを組み合わせて楽しむ)の彼らは、国のために演技はしていない。本当にただ、スポーツを楽しんでいる。ああいったものをどう取り入れていって、オリンピックを変えていくかだ」とも述べた。
JOC委員・來田享子氏も「国を背負って戦う」ことの変化も感じ取っている。「紛争も、いろいろな政治的介入もそうだが、いろいろな線引きは、みんなが自由勝手に引いてきただけ。そういうものを取っ払っていくような発想が、今の時代にはある程度求められている。IOCでも、もう国旗はやめて、国歌もやめて、五輪旗にしてオリンピック賛歌にすればいいでしょうという意見もずっと出てきた」と補足した。
■突きつけられたトランスジェンダー選手問題