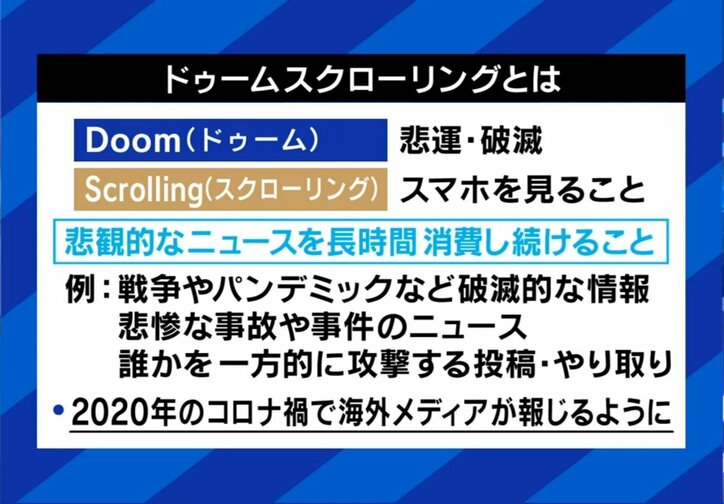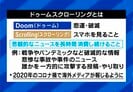■育児に悩む割合は男女に差がないデータも
まず「父親の産後うつ」という言葉を整理する。学術的には「paternal(父親の)postpartum(産後)depression(うつ)」と表現され、これがそのまま直訳されたものと思われる。産業医・産婦人科医でDaddy Support協会・代表理事の平野翔大氏によれば、産後うつの要因は環境のダイナミックな変化、症状は「何も楽しめない・倦怠感が強い」などがある。女性のホルモンバランスが崩れることによる不調は「マタニティーブルー」と呼ばれるが、日本の場合は、これも産後うつに含めてしまうため、今回のように「父親の産後うつ」という表記に異を唱える声が出たと見られている。
平野氏は、産後うつが母親のホルモンバランスによるものばかりと認識されることの危険性を訴える。「産後うつを、産んでいること、ホルモンのことと紐づけている状態は、非常に危ない。ホルモンが乱れるからうつになるのではなく、その人が置かれている社会的状況や支援の問題が非常に大きく関わっている。特にうつ病になると、それを絶対無視してはならないし、ホルモンだけで病的なうつ病を語るのは、むしろ女性の置かれている環境を見過ごすことにすらなりかねないし、危うさを感じる」。
ある調査では「産後1年間にメンタルヘルスの不調のリスクあり」と判定された人の割合は、父親が11.0%、母親が10.8%、夫婦どちらかが15.1%、夫婦両方が3.4%。また父親の産前・産後のうつの影響には、育児の質・量の低下、子どもとの愛着形成の阻害、虐待リスクの増加、子どもの発達の鈍化などが挙げられている。
■りんたろー。「大好きな人が変わっていくのを目の前で見る苦悩もある」